やっぱり「夫婦同姓制度」がええわ!
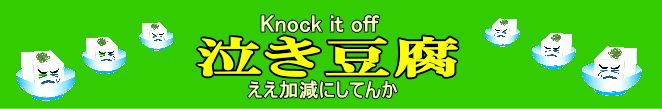
やっぱり「夫婦同姓制度」がええわ!サニー爺は思うんや
「選択的夫婦別姓」なんていう概念が議論され始めたのは
1990年代後半から1990年代前半にかけてのことやそうや。
1970年代に男女平等や女性の権利を求めるフェミニズム運動が
活発になってきて、その中で結婚後の改姓が
「女性の不利益につながる」と言われだしたのが始まりみたいや。
1985年には「男女雇用機会均等法が成立。
同年「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約(CEDAW)に日本が批准。
これを受けて、夫婦同姓の強制が「女性差別」と
みなされる可能性があるとの議論が出始めたんや。
同年に「男女雇用機会均等法」が施行され、
社会全体で男女平等が意識されるようになったんやてぇ。
1987年:「夫婦別姓を考える会」発足
この団体さんは、夫婦同姓が女性のキャリアや
社会的アイデンティティに不利益をもたらすと主張しはりました。
政治的な議論の開始(1990年代~2000年代)
① 1996年:「法制審議会」が選択的夫婦別姓を答申。
② 2001年:「選択的夫婦別姓制度を求める市民運動」が活発化。
自民党を中心とする保守派が「家族の一体感が損なわれる」
として反対し、法改正は進まへんかった。
近年の議論(2010年代~現在)
① 最高裁の判断(2015年・2021年)
2015年:最高裁は「夫婦同姓は合憲」との
判決を下しはりました。ただし、
一部の裁判官が「選択的夫婦別姓の議論は必要」と
意見を述べてはります。
2021年:再び合憲判決。ただし、
「社会状況の変化により、国会での議論が望まれる」
と付言してはります。
② 政府・国会での議論の停滞
2020年以降も、選択的夫婦別姓に関する
法案が提出されたけれど、成立には至ってまへん。
一部の自治体では、「事実婚」や「通称使用」を
認める動きも広がってたようや。
このように、「選択的夫婦別姓」は1980年代からの
男女平等運動を背景に提唱され、
1990年代以降に法制化の議論が進められたものの、
いまだに実現しとりまへん。
なんでやろ?
夫婦同姓制度の意義とメリット
① 家族の一体感と社会的、心理的安定
夫婦同姓制度は、家族が「姓」という形で
一つの単位を作るのやから、
社会的・心理的な安定をもたらしますがな。
同じ姓を持つことで、家族の絆がより強まりよるし、
親子の関係も社会的に認識されやすくなるわなぁ。
これは、日本社会で「家族単位」が重要視されている
伝統と一致してるやん。
② 戸籍制度と辻褄が合うし行政面で効率がようなるでぇ
夫婦が同じ姓を名乗ることで、戸籍制度の管理が一貫し、
行政手続きの簡素化につながるでぇ。
日本の戸籍制度は、「家」を単位としとるから、
夫婦同姓が基本になっていることで、
戸籍上の関係性が明確になりよるなぁ。
もし夫婦別姓が認められたりしたら、
戸籍の管理が複雑化するし、
行政コストが増大する可能性かてあるやんか。
③ 日本の伝統文化との相性
日本の家族制度は、長年「家制度」を
基盤として成り立ってきとるのや。
夫婦同姓は、その延長線上にあってやで、
家族単位を大切にする日本の文化と親和性が高いやんか。
伝統的な価値観を重視することで、
日本社会の安定やアイデンティティを
守ることができますよねぇ。
④ 子どもの福祉面で見ると
夫婦同姓やったら、子どもがお父さんと苗字がちゃうとか
お母さんと苗字がちゃうなんてことがなくなるのやから、
自分は誰や、誰の子やのような混乱を防げるなぁ。
夫婦別姓を導入すると、
子どもがどちらの姓を名乗るかで
トラブルがおきる可能性があるのやないか。
家族が同じ姓を名乗ることで、
社会的な一体感や連帯感が維持しやすくなるでぇ。
皇室の伝統との関わり
① 皇室は伝統的な家制度を維持してはる
日本の皇室は「万世一系」を重視しておられ、
家系を守ることを最優先にしておられます。
天皇陛下の家系は「皇統」として継続され、
婚姻制度もこれに基づいておられます。
皇族は姓を持たず、
皇統としての一体感を維持することが求められています。
② 皇室の伝統が国民の模範に
皇室の家族制度は、日本の家族観や価値観に
影響を与えてきてくれはります。
夫婦同姓は、国民の間でも「家族の一体感」を
保つための重要な要素として位置づけられてきとります。
こうした伝統が、日本の社会秩序や
道徳観の元となってると思うてます。
夫婦同姓制度を維持せなあかん四つの観点
① 社会統合の観点
家族制度の安定は、社会の安定につながる。
夫婦同姓を維持することで、
家族のまとまりが強まり、社会的統合が保たれる。
② 行政コストの観点
夫婦別姓を認めると、戸籍制度の管理が複雑になり、
行政コストが増大する、
とまた増税をあの省が言い出しはりまっせ。
逆に、夫婦同姓の維持によって、行政手続きが簡素化され、
国民全体の負担が軽くなるのとちゃいまっか。
③ 文化・伝統の受け継ぎ
夫婦同姓は、日本社会の歴史的・文化的背景に
しっかり根ざしてまっせ。
伝統を守ることは、国民の自意識を
維持することにもつながるやないか。
④ 子どもの福祉と教育
夫婦別姓やと子どもが両親と異なる姓を持つことで、
心理的な影響が生じる可能性があるでぇ。
夫婦同姓の制度を維持することで、
子どもにとって安定した家庭環が提供できるのや。
やっぱり「夫婦同姓がええやん!」か
日本の伝統的な家制度を維持することは、
社会全体の秩序や文化を守る上で
重要な役割を果たしているし、
皇室の伝統とも一致していると思えますのや。
極端な言い方かも知れへんけど、
大元は天武天皇(飛鳥時代)に作られた
「庚午年籍(こうごねんじゃく)」(670年)やと思いますねん。
それが701年の 「大宝律令」 では、戸籍が正式に制度化され、
6年ごとに作成されることが決められましたのや。
ついでに付けたしやけど、これにより、
土地の分配(班田収授法)や税の徴収(租庸調制度)が
行われるようになったそうや。
日本の戸籍制度は、1300年以上の歴史を持っておって、
現行の「夫婦同姓」にもつながってるのとちゃうか。
そうや、「夫婦同姓」は日本人のDNAに組み込まれとるのや。
それでもって社会の安定と行政の効率化を支える基盤として
機能しているのやと思ってます。
高市早苗さんが言うてはる
「戸籍上のファミリーネーム、家族一体とした氏は残す」
「旧姓、通称使用を法制化」に賛成や。
「選択的夫婦別姓」は1990年代以降に法制化の議論が
進められたものの、いまだに実現してぇへんのは、
皆の心のどこかに伝統と歴史に培われた
戸籍制度のことがあるからとちゃうか。
いつまでたっても決められへん「選択制夫婦別姓」の議論は
もうこの辺で「ええ加減にしてんか」
“Knock it off!”
2025/04/02
SunnyG(サニー爺)


